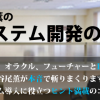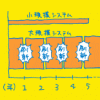IT投資とは?注目される背景やメリット・攻めのIT投資と守りのIT投資の違いを解説

「IT投資」という言葉を聞いたことはありますか?新時代の投資アプローチとして、近年注目を集めています。なぜIT投資が注目を集めているのか、いろいろな背景があるので紹介します。
IT投資が注目されているのは、ITに関する資産を運用することでさまざまなメリットが期待できるからです。どのようなメリットがあるかについても見ていきましょう。メリットがある一方、課題もあります。主な課題についても紹介するので、投資を始める前に頭に入れておきましょう。
IT投資には攻めの投資と守りの投資の2種類あります。攻めと守りの違いについても見ていくので、投資戦略を立てる際の参考にしてください。
IT投資とは?注目される背景や対象も解説

IT投資について、詳しくはわからないという人のためにそもそもIT投資とは何かについて、まずは見ていきます。なぜIT投資が脚光を浴びているのか、その背景についても解説します。どのようなものがIT投資の対象になるかについても紹介するので、IT投資をこれから本格的に始めたいと思っている人は参考にしてください。
IT投資とは?
IT投資とは設備投資の一種で、ITを駆使して新事業の提案や開発を行う方法です。IT関連であれば、すべてIT投資になるので広範囲にわたります。
具体的にはバックオフィス系でシステムを導入する場合もIT投資に該当します。営業系で新システムを導入する場合も、IT投資の一環です。
日本ではIT投資と非IT投資に分けてみた場合、これまで非IT投資の方にはるかに多くの資金が投入されてきました。現状はあまり変わらないものの、徐々にIT投資にも活性化の兆しが見えてきているのもまた事実です。
さまざまな場面で使えるITツールがいろいろと出てきていますし、業務面でもコスト面でも投資すれば大きなリターンが期待できます。これからの時代会社が生き残りをかけるために、IT投資を推進するのも重要な戦略の一環と言えます。
IT投資が注目される背景
なぜIT投資が注目されているのか、それはITの急速な普及です。今や業種関係なく、ITなしではビジネスが成り立たない状況です。DX推進は、どの業界でも喫緊の課題と言えます。
さらに日本は現在、少子高齢化の真っただ中です。今後現役世代が減少することで、人材不足はますます深刻になってくるでしょう。IT投資を進め、業務のデジタル化を整備することで必要最小限の人材でも業務を切り盛りできます。
コロナ禍を経て、リモートワークが新たなワークスタイルとして日本でも定着しました。リモートワークもIT投資なしでは実現できません。リモートワークOKにすれば、通勤圏外の人材でも採用可能になります。
人材不足対策のために、IT投資を真剣に検討すべき時期に差し掛かっていると思ってください。
IT投資の対象
IT投資の対象は、ITに関わるものであれば基本的にすべて該当します。具体的にはハードウェアやソフトウェア、セキュリティ対策などです。さらにコンサルティングなどITサービスや回線の整備、ホームページの作成などもIT投資と言えます。
ITRは「IT投資動向調査」を発表しています。2025年に新規導入可能性では、生成AIが1位になりました。ついでAI/機械学習プラットフォームが続く順位です。AI分野に対する注目が高まっているので、必要に応じてAIへの積極的な出資を検討すべきです。
IT投資を行う4つのメリット

IT投資が注目を集めている要因として、実際に投資することでさまざまなメリットを享受できるからが挙げられます。具体的にどのようなメリットが期待できるのか、主な利点についてここで見ていきます。
①業務の効率化が期待できる
ITを導入することで、業務効率化が期待でき、生産性が向上するのはメリットです。たとえば各業務を支援できるソフトやプログラムを導入することで、余計な作業を省けます。これまですべての項目を人の手で入力しなければならなかったものが、必要最低限の入力で後は自動計算できれば作業時間を大幅に短縮できます。
効率よく作業ができれば、特定の分野に関わる人員を削減できるでしょう。削減できた人材を別の部署に回すことで、さらなる業務効率化が期待できます。
効率化が図れれば、従業員にかかる業務の負担を軽減できます。心身両面のストレスも緩和でき、ワークライフバランスの整った職場として好意的に評価されるでしょう。
②販促力の拡大が期待できる
販促力の拡大効果が期待できるのも、IT投資を実施するメリットの一つです。営業系のシステムやマーケティングツールを積極的に活用することで、自社商品やサービスの周知徹底が図れます。
また近年販促活動で無視できない存在になっているのが、SNSです。SNSで情報発信して、ユーザーの注目を集めれば、自主的に情報拡散してくれます。いわゆる「バズる」状態になり、広く製品をPRできるわけです。
これらの販促ツールを組み合わせることで、販促力の一層の強化が期待できます。業績向上につなげられ、新規事業など今後の経営戦略の選択肢を広げられるのもメリットです。
③スモールスタートが可能
IT投資を進めれば、スモールスタートも可能な点もメリットと言えます。ITツールやアプリを活用することで、人員を大勢集める必要はありません。人件費も必要最小限のコストから始められるわけです。
ITツールは多岐にわたるので、自分の身の丈に合ったレベルで始められます。ITツールの中には、無料で利用できるものもあり初期投資も必要最低限のレベルで事業を立ち上げられます。
このように初期コストを抑制できると、利益が少しあがれば回収期間の短縮化も可能です。費用対効果を重視して新規事業したければ、IT投資は欠かせません。
コストを少なく抑えられれば、たとえ既存のツールが自分のビジネスにマッチしなくてもすぐにほかのツールに切り替えられます。お試し感覚でIT投資できるのも強みの一つです。
④コストの最適化ができる
コスト最適化が可能なのも、メリットの一つです。ITツールを駆使すれば、さまざまなデータを蓄積できます。蓄積されたデータを解析することで、コストが適正かどうか、コストカットできる部分があるかなども発見できます。
コスト最適化をこまめに進めることで、それぞれの法人に合ったスリムな経営が可能です。結果的に効率的に利益を上げられる企業に成長できるわけです。
IT投資を進めれば、紙資料も必要なくなります。紙資料を作成する際に必要なペーパー代や印刷代などもカットでき、この側面からもコスト最適化を進められます。
IT投資の課題

IT投資は魅力的な側面がある半面、克服すべき課題がいくつかあることにも留意してください。IT投資を推進するためにどのような課題を克服しなければならないか、以下で挙げていきます。
経営陣のITに対する理解が浅いと稟議が通りにくい
ITの導入を提案しても、経営陣がITに関する理解に乏しいと稟議の通らない可能性がある点は懸念されます。もし現状とくに経営上問題なければ、ITへ積極投資しなくても良いと考えてしまうからです。
「現状で問題ないのに、なぜわけのわからないものに投資する必要がある?」となるわけです。別項で紹介しますが、IT投資の場合費用対効果が見えにくいところもあります。
もしIT投資計画を稟議にかけても否決してしまったのであれば、なぜなのかを分析しましょう。そしてITに関する理解に浅い経営者でも納得させられるような必要性を訴えるにはどうすれば良いか、検討してください。
使用するツールが増えるとコストの種類も多くなる
IT投資した場合初期費用のほかにも、ランニングコストもいろいろと必要です。業務効率化を目指して広範にIT導入したところ、コストの種類が増えてしまって、コストマネジメントがうまくいかなくなる恐れもあります。
さまざまなツールを導入した結果、費用の全体像を把握できなくなっては元も子もありません。結果知らず知らずのうちに想定外の大きな出費を強いられている可能性もあります。
もしIT投資を行うのであれば、初期費用やランニングコストがいくら程度かかるのかシミュレーションしておきましょう。そしてこまめにツールごとのコスト状況を把握することも大切です。
IT投資の費用対効果がわかりにくい
IT投資の課題として、費用対効果が測りにくい点も留意しなければなりません。まず顧客満足度やセキュリティなど、数値化するのが難しい評価要因もあるからです。数値化できない部分があるために、本来よりも過小評価されがちな点はネックです。
またIT投資の種類によっては、費用対効果のなかなか出にくいものがあるのも課題と言えます。システム投資であれば、比較的短期間で効果が出やすいので問題ないかもしれません。
しかしプロジェクトによっては、費用や投資額が終盤に差し掛からないとはっきりしない場合もあります。またパフォーマンスの評価もどの段階で行うかによっても、違いが出てきてしまいます。長期的視野に立っての効果を狙っている場合、事前にどの程度効果が期待できるか判断しにくい部分があるわけです。
もしIT投資に関する評価をしたければ、費用対効果以外にもITに投資しなかった際のマイナスの影響について、シミュレーションするのがおすすめです。IT導入しないと従業員が減ったときに対応しきれなくなる、ライバルがシステム化を進めていった場合、取り残されるといったことを説明すると良いでしょう。
ITツールで解決できるものには限りがある
ITツールがすべての課題のソリューションになり得ないことも問題点の一つです。極端な話、人の感情をコントロールできませんし、従業員を経営陣の思い通りに動かすこともできません。
IT投資が良いというので安易に飛びつくのではなく、わが社にはどのような課題があって、ITを導入することでどのように解決できるかを考えましょう。このことを検討しないとお門違いのITツールを導入したり、ツールをうまく使いこなせずにせっかくのIT投資の恩恵に十分あずかれなくなったりしかねません。
IT投資の日本における動向

我が国のIT投資における現状はどうなのか、気になるところでしょう。日本の投資額を見てみると、非IT投資の方がIT投資よりも大きい状態が続いているのは先に紹介した通りです。2012年の調査でも欧米企業のIT投資は売上高の約3.6%でした。対して日本のIT投資の割合は、1%です。IT投資額の日本企業の少なさは顕著です。
引用元:次期システム開発体制を立ち上げる時に知っておくべき7つのトレンド
しかし近年IT投資額も着実に増加しているので、最近における推移についてまとめました。
IT投資額を増額した企業は2021年度以降増加
ITRの発表している「国内IT投資動向調査報告書」によると、IT投資額を増額したと回答した企業は2021年度以降増加の一途をたどっています。この流れは大企業だけでなく、中堅企業も同様なので事業所の規模に関係なくIT投資が活発に行われていることがうかがわれます。
2025年度にはIT投資の増額を見込む企業は45%に達しました。これは2001年の調査開始以来最高値になります。
国内のIT投資が活性化した背景には、コロナ禍も影響しているでしょう。不要不急の外出や人との接触抑制などで、リモートワークやテレワークが急速に普及しました。その結果、ITインフラの整備に力を入れる企業が増えたわけです。
DX関連へのIT投資額が多いのは製造・卸売業界
業種別にDX関連への予算が全体に占める割合で大きいのは、製造業でした。続いて卸売や小売が上位を占める結果になっています。とくに今後IT投資が積極的に進められる業界として、注目されているのが卸売・小売です。
中小企業庁が発表している「中小企業白書」の2022年版を見てみると、向こう5年間のIT投資計画で卸売の増加予定の割合が業種別で最も多かったとしています。5%以上の増加を見込んでいると回答した企業は、3割超に達しました。
しかもこれまで5年間の傾向を見ても、増加傾向と回答した企業は4割以上ありました。長期にわたって、安定してIT投資の増額を進めていることがうかがえます。
攻めのIT投資と守りのIT投資の違い

IT投資の中には大きく分けて、攻めの投資と守りの投資があります。これから投資戦略を策定するためには、攻めと守りどちらを重視するか検討しなければなりません。ここでは攻めと守りのIT投資の特徴について、それぞれまとめました。
従来のIT投資を見てみると、防御的なスタイルが主流でした。しかしこれからの時代、攻めのIT投資にも重点を置いた方が良いのではないかと見られています。守りに力を入れれば負けることはない半面、勝つこともできません。守りの投資にも十分配慮しつつも、顧客接点に立った攻めの投資も検討していきましょう。
攻めのIT投資とは?
攻めのIT投資とは、企業の成長を加速させるような戦略性の高い投資のことです。競争力の強化やイノベーションの推進を目的としたもので、新たな事業価値を創出する目的の投資も攻めに該当するでしょう。
具体的には、新たなビジネスモデル構築のためのIT活用が挙げられます。近年ではIoTやAIを使った経営も注目されていますし、ビッグデータも今後のIT戦略のカギを握るジャンルと言われています。
先ほども紹介したように、顧客接点への投資も攻めの戦略と言えるでしょう。顧客体験を向上するようなマーケティングツールやデータ分析デバイスの導入などです。顧客体験を向上することで顧客満足度を高め、企業価値の向上が期待できます。
DX化を推し進めるのも攻めの投資の一環です。既存業務の革新をもたらすのはもちろんのこと、新規市場開拓も可能です。最新技術を導入することでビジネスモデルの改革が期待できます。
守りのIT投資とは?
守りのIT投資とは、リスクマネジメントを目的としたものだと考えてください。円滑に業務を進め、安定した経営を継続するためのIT投資になります。
守りの投資では、主にインフラ構築が該当すると思ってください。インフラ整備することで、システムの安定性が担保されます。その結果トラブルの発生リスクを抑制し、損失を最小限に抑えられるでしょう。
具体的には、セキュリティ強化のための投資が挙げられます。サイバー攻撃や情報漏洩のリスクを防止できるからです。
またBCPも企業運営において無視できない守りのIT投資です。BCPは日本語に訳すと「業務継続計画」となります。災害やサーバーダウンなどの問題が発生した際のスピーディな復旧体制構築を目的とした計画です。日本は地震や台風など自然災害はどこでも起こりうるので、いざという時のために計画を策定するのは重要です。
既存システムの維持や運用も守りのIT投資の一種と言えます。ITインフラも時間の経過とともに老朽化するので、最適化することも重要な戦略です。
IT投資の評価方法
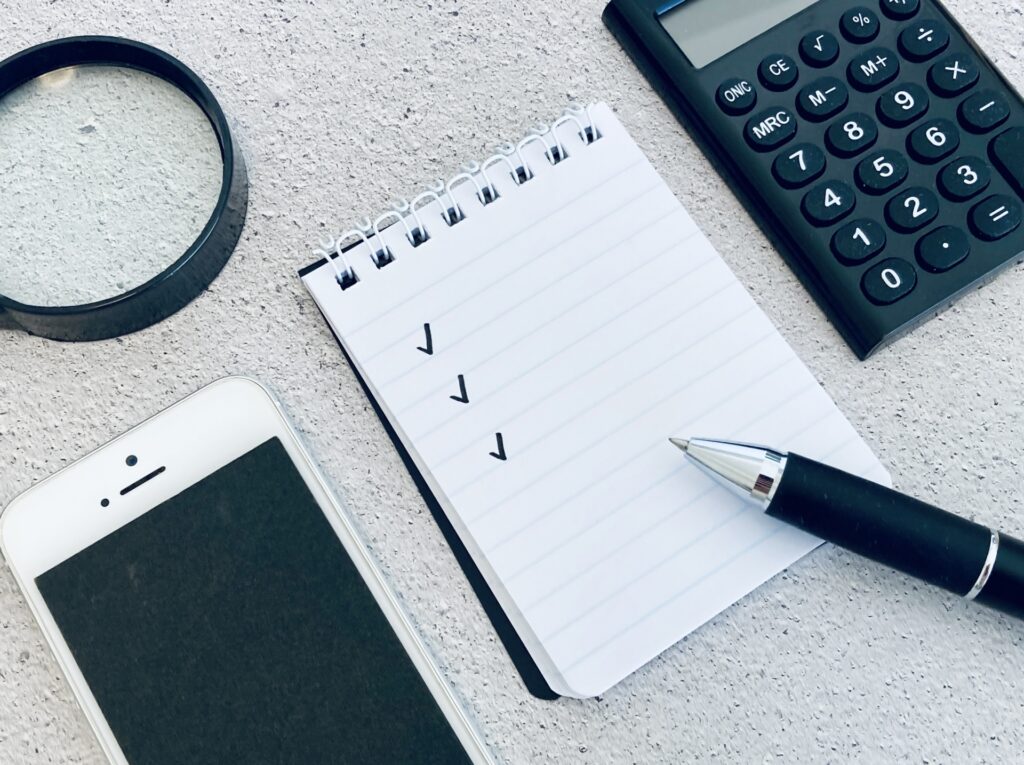
IT投資の評価を検討するにあたって、重要なのは投資をした結果どうなりたいのか、その目的をはっきりさせることです。そこで重要なのは、大きな目標にいたるまでのプロセスにおいて小さな目標を設定する点です。
たとえば最終目標が「業績○%アップ」だったとしましょう。しかしそれまでに「業務効率化で作業時間○%減」や「従業員の負担軽減で定着率○%アップ」などの目標を立てる形です。目標を細分化することで、IT投資の評価がアップします。
稟議を通しやすくするためには、客観的な目標を設定するのも大切です。数値化できるような目標設定にすることで人々も納得しやすくなり、稟議で認められる確率も高まるわけです。
IT投資の評価において、投資対効果を意識してください。ITに投資した結果、どの程度の利益が残るかを念頭に置きましょう。ITへの投資では初期費用だけでなく、ランニングコストも含めて考えましょう。
効果に関しては収益のほかにも、いろいろな要因が想定できます。利便性向上に伴う顧客満足度の改善、作業効率アップに伴うリソースの再配分による新規顧客の開拓なども含まれるでしょう。投資と効果として、どのような評価軸が考えられるか慎重に検討しましょう。
IT投資の成功事例

日本でもIT投資を推進している企業が増加傾向にあることは、すでに別項にて紹介しました。ここではIT投資による日本での成功事例として、2つピックアップしてみました。いずれも攻めのIT投資によって成功した事例なので、今後の戦略を練る際の参考にしてください。
アサヒグループホールディングス株式会社
アサヒグループホールディングス株式会社では経営理念の中で、DXを「稼ぐ力の強化」や「新たな成長の源泉」「イノベーション文化情勢」の原動力ととらえています。さらに「Asahi Digital Transformation」としてDX戦略を10個の具体的なテーマに分け、戦略マップを作成しています。
その結果、商品パッケージのデザイン作成でAI技術を活用したり、VR商品パッケージ開発支援システムの開発を行いました。食品業界でも業務プロセス刷新が求められているので、時代の要請に応じる形でIT投資を推進しているわけです。
株式会社小松製作所
株式会社小松製作所は2020年のDX銘柄でグランプリに輝いた企業です。その中で「製造業におけるデジタル化の先駆け的企業」と評価されました。
なぜ高い評価を得られたのか、「コムトラックス」が大きかったと言われています。工場内と各拠点の機械をネット上で一括にて稼働状況を管理できるシステムです。元は機械の盗難防止で開発されたシステムですが、現在では部品交換や燃費の効率化を顧客に提案するためのツールにも活用されています。
コマツでは2019年に中期経営計画を策定しました。その中で、「スマートコントラクション」と呼ばれる方針を打ち出しています。顧客はもちろんのこと、業界や社会の課題をテクノロジーによってソリューションするアプローチです。
IT投資についてご相談はオーシャン・アンド・パートナーズまで

欧州の企業と比較して、日本ではIT投資になかなか理解の得られない状況が続いていました。しかし2020年に発生した新型コロナウイルスの世界的な流行で、リモートワークやテレワークが必要になりました。その結果、近年IT投資に力を入れている企業は増加傾向です。
IT投資をする際には、ITシステムを導入することでどのような恩恵が受けられるのか、会社にどのようなイノベーションをもたらすかを検討しましょう。投資対効果の分析を進め、改善すべきポイントはないかこまめに検証しなければなりません。
システム開発のオーシャン・アンド・パートナーズでは「基幹システム再構築の成功法則大全」を配布しています。基幹システムを再構築し、プロジェクトを成功に導くための方法や心構えに関して紹介したファイルです。発注者やベンダ、現場と異なるフェーズで作業していると認識の違いなどが生まれるものです。自分たちの意識にこだわると衝突してしまうので、時には妥協できるラインを見出すことも必要になります。このようにシステムを再構築する場合にどのようなポイントに重きを置くかについて解説しているので、参考にしてみると良いでしょう。
IT投資についてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人について
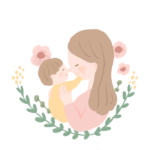
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。