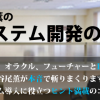RFPとRFIの違いとは?記載する項目や作成する4つのメリットを徹底解説!
本記事では、RFPとRFIの違いについてわかりやすく解説します。
「RFP(提案依頼書)」とは、システム導入を発注したい企業が、候補となるベンダーにプロジェクトの概要や要望などを提示するための文書です。よく似た言葉に「RFI(情報提供依頼書)」があり、複数のベンダーの技術・製品に関する情報提供を依頼するためのものです。
これら2つの文書を適切に作成することで、効率のいいベンダー選定が可能になります。
この記事では、それぞれの違いだけでなく、文書に記載する項目やその他の間違えやすい言葉・用語などについても詳しく紹介します。
ITシステムの導入を検討している企業の方に役立つ情報をお伝えしますので、ぜひ最後まで目を通してください。
RFPとRFIのそれぞれの意味とは?
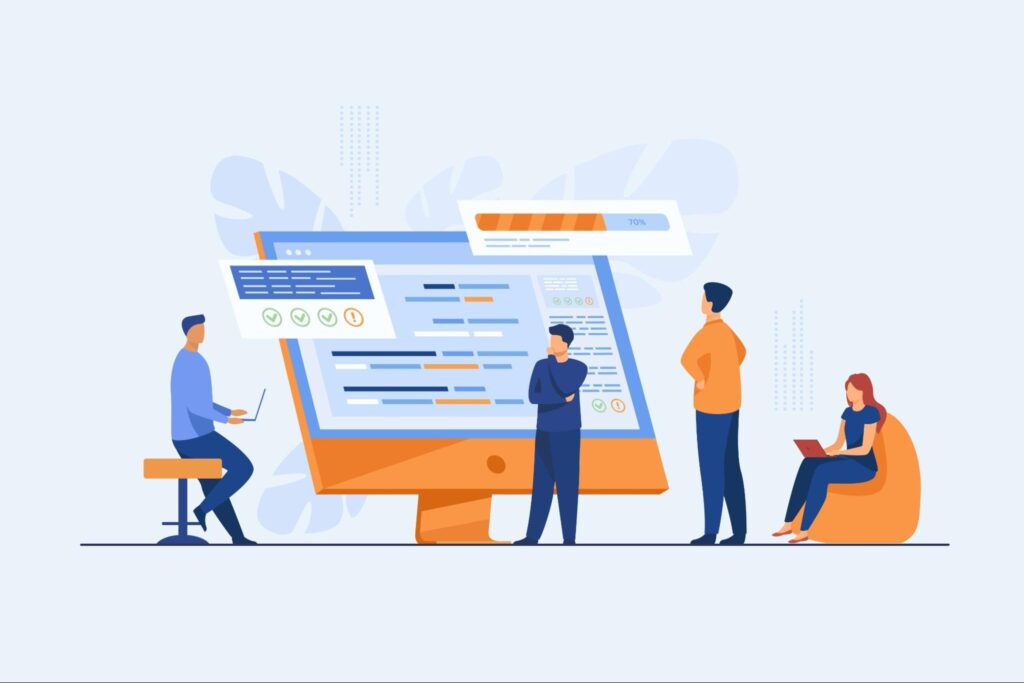
RFPやRFIは、どちらも企業のシステム導入プロセスにおけるベンダー選定のための重要な文書です。
名前が似ているため間違えやすい用語ですが、それぞれの文書の内容や役割は全く違います。
まずは、RFPとRFIの意味の違いやメリットなどについて詳しく解説します。
RFP
「RFP(提案依頼書)」とは、システム導入を発注したい企業が、候補となるベンダーにプロジェクトの概要や要望、制約などを提示するための文書です。受け取ったベンダーは、文書の内容を踏まえて、具体的な提案を行います。
適切なRFPを準備することで、より的確な提案を受けることができるため、自社の課題解決に最適な発注先を見つけやすくなります。
| RFP(Request For Proposal:提案依頼書) | |
| 目的 | プロジェクトの要件を明確に伝え、最適なベンダーを選定するため |
| 発行するタイミング | プロジェクトの要件や制約が明確になった段階 |
| 記載内容(例) | ・プロジェクトの概要 ・目的とゴール ・システムの仕様 ・予算・納期 ・要望事項 等 |
| 求める回答 | 具体的な提案や見積もり、スケジュール等 |
RFPには、「自社がどのようなシステムを求めているのか」を詳しく記載します。例えば、プロジェクトの目的やゴール、求めるシステムの仕様、予算などの要望・制約などです。
RFPを作成することで、発注側の意図を明確に伝えられるため、ベンダーとのやりとりが円滑に進み、認識のズレを防ぐことができます。逆に、RFPを作成しない場合、細かい調整が必要になり、手間が増えてしまうこともあります。
RFI
RFPと似た言葉に「RFI(情報提供依頼書)」があります。RFIとは、ベンダー選定の前に各企業の技術・製品に関する情報提供を依頼するための文書です。
RFIを送付することで、複数のベンダーから情報を集め、どの企業が自社のニーズに合うのかを判断しやすくなります。
| RFI(Request For Information:情報提供依頼書) | |
| 目的 | 検討材料のための情報収集・市場調査 |
| 発行するタイミング | 発注先候補の選定前 |
| 記載内容(例) | ・自社(発注者)の情報 ・ベンダーの基本情報 ・ベンダーのサービス・製品 |
| 求める回答 | 企業の基本情報、技術情報、製品情報など |
発注者が新たなシステムの導入を考えている場合、市場にはどのようなシステムがあるか、それぞれの製品の特徴やおおよその価格感、導入に必要な条件などの情報を集める必要があります。それらの情報を入手するために、発注側がRFIを発行し、複数のベンダーに送ります。
文書には、発注側のプロジェクトの趣旨や機能要件等の情報と合わせて、相手企業と製品・サービスの基本情報を問う項目を用意します。特に、企業のWEBサイトやカタログに掲載されていない情報に関する質問が中心となります。
RFPとRFIの違いとは?使われる場面について詳しく解説!

ここまで、RFPとRFIの意味についてご紹介してきました。では、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
それぞれの特徴や使われる場面について、さらに詳しく見ていきましょう。
①求める情報の具体性
RFPとRFIの大きな違いとなるのが「どのくらい具体的な情報を求めるか」です。
RFP(提案依頼書) は、システム開発やサービス導入を考えている企業が、具体的な提案を求めるための文書です。ベンダーは、RFPをもとに詳細なプランや見積もり、スケジュールなどを提示します。
RFI(情報提供依頼書) は、ベンダーを決める前の情報収集のために使います。つまり、ベンダーに自社のニーズに合った技術やサービスがあるかどうかを確認するために送付するものです。
この段階では具体的な提案は求めず、基本的な情報提供を依頼するのが目的になります。
②活用するタイミング
RFIは、企業がベンダーから情報を集め、広く情報を把握する段階で作成されます。そのため、RFIはベンダー選定の初期段階で活用する文書です。
一方、RFPは、RFIで収集した情報をもとに、ベンダーに対して具体的な提案を依頼します。つまり、選定プロセスの後半に使用されるものです。
このように、RFIとRFPは活用するタイミングにも違いがあります。
③発行するベンダーの件数
RFIとRFPでは、発行するベンダーの件数も違います。
RFIは幅広い情報収集が目的なので、比較的多くのベンダーに送付する傾向があります。その後、RFIの回答をもとに候補となるベンダーの数を絞り込み、RFPを発行することになります。RFIを送付したからといって、RFPを送らなければいけない訳ではありません。
さまざまなケースがありますが、一般的にRFIはおよそ10~12件、RFPは3〜4件のベンダーに対して発行・送付するのが一般的です。
【関連】RFPやRFIとよく間違われる言葉について

RFPとRFIの違いを押さえたところで、この2つの用語と間違われやすい言葉についてご紹介します。
以下の3つの用語はそれぞれRFPやRFIに関連する言葉ですが、意味や目的は異なります。それぞれの意味を理解しておくことで、ベンダー選定におけるやりとりがスムーズになるので、ぜひ目を通してみてください。
| RFQ | Request for Quotation: 見積依頼書/見積要求書 | ベンダーに価格や内訳の開示を依頼するために発行する文書 |
| RFx | RFP:提案依頼書 RFI:情報提供依頼書 RFQ:見積依頼書の総称 | ベンダー選定における3つの重要な文書/プロセスの総称 |
| RFC | Request for Comments: 意見招請 | 企業・行政機関の入札・発注前に、専門家や関係者から仕様書に関する意見やコメントを募集すること |
RFPやRFIに記載する必要のある項目とは?

RFPやRFIに記載する項目には、特に決まりはありません。
ただし、文書を作成する際には、文書を策定する企業の状況や目的、解決したい課題に合わせた項目を盛り込む必要があります。プロジェクトの目的やゴールを明確にして、抜け漏れのないように項目を準備することが、プロセス成功の鍵を握ります。
ここからは、RFIとRFPの一般的な構成要素やポイントについて分かりやすく紹介していくので、文書作成の際に参考にしてください。
RFIに記載する項目
RFIでは、自社の目的や背景を明確に伝えたうえで「その課題に対してどのようなソリューションがあるのか」という情報提供を求める必要があります。
つまり、企業のコーポレートサイトや会社案内で公開されていない「情報」を提供してもらうことが、この文書の趣旨となります。
記載する項目に決まりはありませんが、基本的には以下の5項目が必要です。
- 目的・背景
- 自社の基本情報
- ベンダーの基本情報
- ベンダーの製品・サービスの基本情報
- 製品・サービスの機能要件
目的・背景
まずは、今回なぜRFIを発行したのか、その目的や背景を明確に伝えましょう。
- 目的:ベンダーに対してどのような情報提供を求めているのか
- 背景:現在自社でどのような課題を抱えているのか
この項目をはっきり記載することで、ベンダー側が適切な回答を準備しやすくなります。
自社の基本情報
RFIを作成する際は、自社の基本情報を明記することが大切です。自社の事業規模や組織図などを開示することで、ベンダーはより的確な情報提供ができるようになります。
- 事業概要(業種や提供サービス)
- 会社の規模(従業員数・売上規模など)
- 検討中のプロジェクトが関わる業務範囲
また、ベンダーとは将来的にビジネスパートナーとなる可能性もあるため、関係構築の第一歩としても有効です。
ベンダーの基本情報
自社だけでなく、ベンダーに対しても企業の概要を記載してもらう項目を設けましょう。
- 会社名・所在地
- 売上高・企業規模
- グループ企業・親会社の有無
これらの情報があれば、ベンダーの経営規模や安定性を把握でき、発注先として適切かどうかを判断しやすくなります。
ベンダーの製品・サービスの基本情報
次に、ベンダーが提供する製品・サービスの基本情報について回答を求めましょう。
- 製品・サービスの名称
- リリース時期
- 過去の導入実績
- 製品やサービスの価格(概算)
これらの項目により、ベンダーの提供する製品・サービスが自社の課題を解決できるかどうかを判断しやすくなります。
製品・サービスの機能要件
最後に、候補を比較・検討する上で重要な「機能」に関する項目を準備しましょう。
- 製品の名称・主要機能
- 動作環境
- 使用する開発言語
- サポート体制
各社の製品を公平に比較できるよう、項目はシンプルかつ統一感を持たせることがポイントです。
RFPに記載する項目
FPを作成する際は、まず「どのようなシステムを求めているのか」というプロジェクトの概要を伝え、その後に詳しい要件について説明していく流れが理想的です。
ここでは、RFPに記載する主な項目を3つのポイントに分けてご紹介します。
- プロジェクトの概要(目的や背景など)
- 提案依頼内容(求めるシステムの要件など
- ベンダー選定の進め方(評価基準やスケジュールなど)
プロジェクトの概要
まずは、どのようなプロジェクトなのか、どんなシステムを導入したいのかを明確にします。ここで自社の課題や目指すゴールを明確に伝えることで、ベンダーから精度の高い提案を受け取ることができます。
RFPのプロジェクトの概要には、以下のような内容を記載するとよいでしょう。
- プロジェクトの概要、背景
- 現状のシステムの状況
- 解決したい課題
- プロジェクトの具体的な目的と目指すゴール
- システムの運用計画(人員や環境など)
- 予算範囲(目安や上限) など
提案依頼内容
続いては、提案に盛り込んでほしい項目を記載します。
ベンダー側は自社の強みや実績をアピールする傾向がありますが、発注側としては運用時のサポート体制など、事前に確認しておきたいポイントがあるはずです。あいまいな表現を避け、具体的な要件を示すことが大切です。
RFPの提案依頼内容には、以下のような項目を記載しましょう。
- ベンダーの組織情報
- 提案システムの概要や構成
- 機能要件
- 非機能要件
- プロジェクトのスケジュール
- プロジェクトの体制や管理方法
- 運用時のサポート体制(保守や研修など)
- 費用の見積もり(概算)
- 制約事項
- 同様の製品・サービスの導入実績 など
ベンダー選定の進め方
最後に、提案を受け取った後の選定方法を明確に示します。選定のスケジュールや評価方法を具体的に記載することで、ベンダー側にとっても計画が立てやすくなります。
また、RFPを受け取るベンダーは限られたリソースの中で提案を作成します。そのため、公正な評価体制が整っていることを伝えることが大切です。もし「受注の可能性が低い」と判断された場合、提案を辞退されるケースもあるため注意しましょう。
ベンダー選定に関する項目には、以下を記載するとよいでしょう。
- 選定スケジュール
- 提案の評価方法(評価基準・方針)
- 提出期限
- フォーマットの指定
- 提案の送付先 など
RFPやRFIを作成する4つのメリット

具体的な項目を押さえたところで、続いてはRFPやRFIを作成するメリットについて解説します。
実際には、RFPやRFIを省略して個別にベンダーと交渉を行うことは可能です。しかし、RFPやRFIを作成することで、客観的かつ効率的に発注先を選定でき、明確に目的やゴール、条件を提示したうえで仕事を任せられるため、トラブル回避にもつながります。
こうしたメリットについて、さらに掘り下げてご紹介します。
①幅広い情報収集に役立つ
RFIを作成することで、製品・サービスに関する情報を幅広く把握するだけでなく、市場調査としても活用できます。
たとえば、
- どのベンダーがどのような技術を持っているのか
- 現在のシステム導入コストの相場
- どのような最新技術が活用されているのか
これらの情報を集めることで、自社に最適な候補を見つけるだけでなく、情報を自社の事業展開の材料にすることもできます。RFIはこうした幅広い情報収集に役立ちます。
②客観的かつ公平な選定が可能
RFIやRFPによって、複数のベンダーから同じ項目の情報提供を受けることで、同じ基準でベンダーを比較でき、客観的かつ公平に選定ができます。
特に、規模の大きいプロジェクトでは、公平性の高いプロセスを確保することが大切です。
選定理由を文書に残しておくことで、選定した製品やサービスにトラブルが生じた際の社内対応も円滑に進みます。
③トラブル回避に役立つ
RFPによって事前に要件を明確にしておくことで、プロジェクト実行後のトラブルを未然に防ぐことができます。
たとえば、仕様や要件を整理して伝えることで、発注者とベンダーの認識のズレをなくしたり、期待する成果や条件を明確に提示することで、誤解を防ぐことができます。
スムーズなベンダー選定を進めるためには、RFPが重要な役割を果たすのです。
④明確な目標を理解しベンダーもプロジェクトに取り組める
RFPを通じて、プロジェクトの目的やゴールを明確に伝えることで、ベンダー側もより適切な提案を行うことができます。
さらに、目指すゴールについて発注者とベンダーの認識が一致していれば、効率的なシステム開発・導入が可能になります。大きな機能修正や納期の遅れなどのトラブルなども、最小限に抑えられるでしょう。
RFPは、ベンダーがプロジェクトに適切に取り組むための指針となるため、的確に作成することが重要です。
RFPやRFIを活用する際の流れ
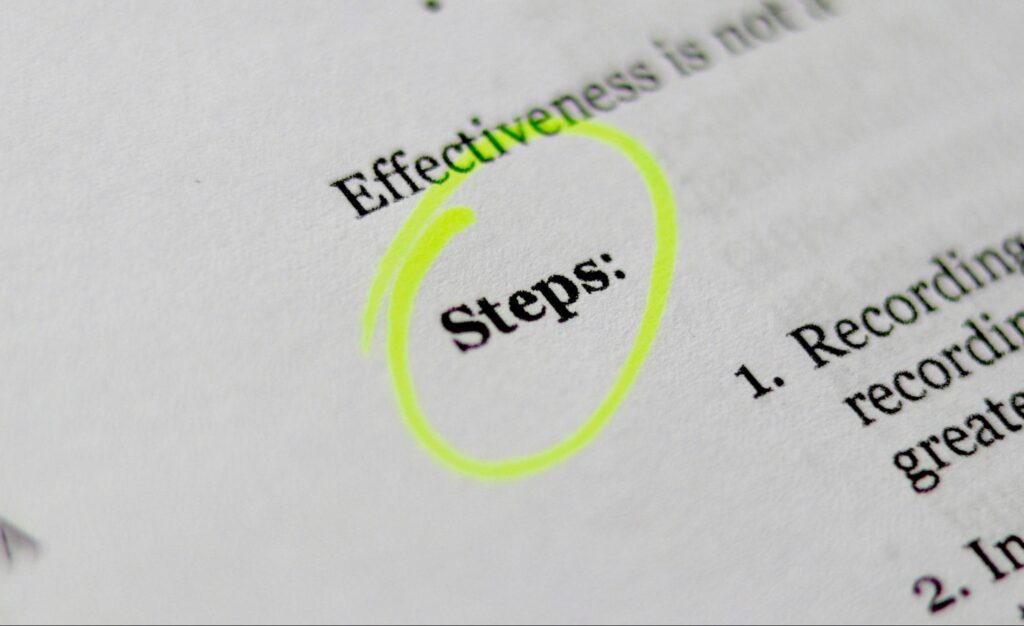
RFPやRFIは実際にどのような段階で発行されるのでしょうか。RFPとRFIを活用する際の流れについて簡単に押さえておきましょう。
- 情報収集:自社のプロジェクトに関連するベンダーの情報を広く集め、市場を把握します。RFIを作成し、該当するベンダーに送付します。
- 提案依頼・選定準備:RFIの回答を受けて、適切なベンダーを絞り込み、RFPを発行します。同時に、提案の評価項目・配点を定めておきます。
- 評価と選定:RFPによる提案を回収し、評価と選定を行います。ベンダーを数社に絞り込み、あらかじめ決めておいた評価項目・配点でベンダーを選定します。
RFP作成をコンサルに依頼するメリット

ここまで見てきたように、RFPは企業のシステム導入のためのベンダー選定の効率化に欠かせない文書です。しかし、いざRFPを作成しようとすると、方向性のブレや項目の抜け漏れが起きることも珍しくありません。
特に初めてRFPを作成する企業や、企業内で専門知識が不足している場合は、コンサルによるRFP作成支援を活用することで、より効果的なRFPを作成できます。
以下、コンサルに依頼するメリットをご紹介します。
まず、コンサルは自社だけでは見落としがちなポイントをカバーした、的確な要件定義が可能です。これにより、より洗練されたRFPを作成することができ、プロジェクトの成功確率を高めます。
また、コンサルの詳細なヒアリングにより現場の声と経営者視点の課題との合意形成を行い、ブレのない一貫したゴールや要望をRFPに落とし込むことができます。現場のニーズと経営方針のすり合わせを行い、企業全体にとって価値のある課題解決を実現することができます。
さらに、リスク管理により予算とスケジュールを最適化するため、プロジェクトの進行を効率化できる点も大きなメリットです。
RFPに対するコンサル支援については、こちらの記事で詳しく解説しています。
RFPについての相談はオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社まで

RFP(提案依頼書)とRFI(情報提供依頼書)は、企業がシステムを導入する際に発注先候補のベンダーへ送付する文書です。RFIは広くベンダーの情報を収集するためのものであるのに対し、RFPは具体的な要件や要望を伝え、詳細な提案を求める点が大きく違います。
特にRFPは、ベンダー選定だけでなく、その後のスムーズなシステム導入にも影響を与える重要な役割を担っています。
当社、オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社では、お客様のRFP作成に関するご相談を承っております。
経験豊富なコンサルタントが、企業全体のニーズを的確に把握し、現場の声と経営層の視点を的確に反映させた、質の高いRFP作成をサポートします。また、リスクマネジメントを考慮し、実現可能な計画を設計することで、より実行性の高いRFPを作成します。
RFP作成に関するお困りごとは、ぜひ当社にお任せください。
まずはお気軽にオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社までお問い合わせください。
この記事を書いた人について
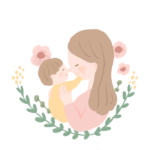
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。