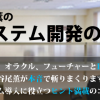RFPと要件定義書の違いは?RFIやRFQとの違いやRFPを作成するうえでの9つのポイントを解説

システム開発の初期段階で登場するRFP(提案依頼書)と、開発が本格化する段階で詳細を詰める要件定義書。どちらもプロジェクトの成功に不可欠なドキュメントですが、その目的と役割は大きく異なります。「一体何が違うの?」「RFIやRFQといった言葉もあるけれど、どう使い分けるのか?」そんな疑問をお持ちの方も少なくありません。
本記事では、RFPと要件定義書の根本的な違いを分かりやすく解説。さらに、情報収集のRFI(情報提供依頼書)や見積もり取得のRFQ(見積依頼書)との関連性も整理します。
そして、ベンダーから質の高い提案を引き出し、プロジェクトを成功に導くためのRFP作成における9つの重要なポイントを、具体的なアドバイスと共にご紹介します。これを読めば、RFP作成からベンダー選定まで、自信を持ってプロジェクトを進められるはずです。
目次
RFPとは?目的や作成者を解説

ここでは、システムの新規構築や刷新時に作成する資料のRFPについて、意味や目的、作成者に分けて解説します。
RFPとは?
システムの新規構築や既存システム刷新の際、発注元企業が準備すべき重要な資料がRFPです。
これは、IT担当者や情報システム部門の担当者などが、自社のシステムで実現したい業務プロセスや克服すべき課題、将来の目標、そしてそれらを実現するための具体的な要求事項を、システムインテグレーターやベンダーに伝えるための書類です。システム導入を検討する際には、RFPの作成が非常に有効な手段となります。
RFPの目的
RFPを作成する最大の目的は、発注企業がシステムベンダーに対して、自社の抱える課題や実現したいビジネスの展望、そしてシステムに求める具体的な要求を過不足なく正確に伝え、双方の共通認識を確立することにあります。
RFPなしに口頭でのみ情報を伝達したり、書面の内容が曖昧な場合、発注側の意図や要望がベンダーに十分に伝わらず、期待通りの提案を得られない可能性があります。
システム開発の専門家であるベンダーも、発注側の内部事情を完全に把握しているわけではありません。したがって、RFPを通じて現状分析(As-Is)と将来のあるべき姿(To-Be)を明確に伝え、双方の認識のずれや情報不足によるリスクを最小限に抑えることによって、発注側が求めるシステム導入が確実になります。
RFPの作成者
RFPは、原則としてシステム開発を外部委託する発注側企業が主体となって作成します。通常、社内の情報システム部門が中心となり、現場の業務担当者や経営層など、関係各方面からヒアリングを行い、その内容を文書にまとめます。
ただし、社内にシステム開発の専門知識を持つ人材が不足していたり、RFP作成のノウハウが無かったりして自社のみでの作成が困難な場合、外部のコンサルティング企業やSIerに作成支援を依頼する選択肢もあります。
RFPと要件定義書の違い

システム開発を外部に依頼する際に準備する書類として、RFPの他に要件定義書が存在します。
RFPは、どのようなシステムを求めているかの大まかな希望や、解決したい課題を記述し、複数の会社に「このようなシステムが構築できます」という提案を募るための書類です。これは、依頼先が未決定の段階で作成されます。
一方、要件定義書は、依頼先が決定した後、「どのような機能が必要か」「画面遷移はどうあるべきか」といった、システムの詳細な仕様を記述するものです。これは、実際のシステム構築のための詳細な指示書となります。
RFPも要件定義書も「どんなシステムが必要か」を伝える点では似ていますが、一番の違いは「何のために作るか」です。RFPの主目的は最適な依頼先を選定することであり、要件定義書の主目的は選定された会社に必要な機能を明確に伝えることです。
RFPとRFIやRFQの違い

RFPと類似した用語にRFI(情報提供依頼書)やRFQ(見積依頼書)があります。それぞれの意味合いや作成のタイミングについて、認識が曖昧な方も少なくありません。ここでは、RFIとRFQの概要、メリット、記載すべき項目について解説します。
RFIとは?
RFI(Request for Information)は、日本語で「情報提供依頼書」と訳されます。発注側企業が、潜在的なベンダーに対して、会社概要、過去の開発実績、保有する技術や製品に関する情報の提供を求める書類です。
通常、RFP作成の前段階で作成され、Webサイトや会社案内だけでは得られない詳細な情報を収集することを目的とします。
一般的な流れとしては「RFIで情報収集と一次選考を行い、その結果を踏まえてRFPを作成し、二次選考を行う」という使い分けがなされます。
RFQとは?
RFQ(Request For Quotation)は、日本語で「見積依頼書」と呼ばれます。これは、発注側の企業がベンダーに対し、システム開発にかかる費用の総額やその詳細な内訳の提示を求める書類です。
システムの具体的な要件が定まらない段階では、見積もりを正確に算出することが難しいため、通常はRFPの後に作成されます。ただし、RFQの作成を省略し、RFPに見積もり依頼を含めるケースもあります。
RFPを作成する6つのメリット

RFPの作成はシステム開発や製品選定のプロセスにおいて、単なる手間以上のメリットをもたらします。ここでは、RFP作成の主要なメリットを6つ掘り下げます。
①自社の要望を正確に伝えることができる
RFPの作成は、ベンダーに自社の要求事項を的確に伝達できる点が最大のメリットです。
必要な要件の伝達漏れや、発注側とベンダー間での認識のずれが生じやすい口頭のみの説明では、期待していた内容と異なる提案が示される可能性が高まります。また、提案内容の修正には余分な時間と労力がかかり、それは双方にとって避けたい負担です。
自社が抱える課題や将来的なビジョンを踏まえた満足度の高い提案を受けるために、また、その後のシステム開発プロセスも円滑に進めるためにも、RFPを事前にしっかりと準備しておく必要があります。
②自社の課題を洗い出せる
RFPを作成するプロセスは「システムを通じてどのような問題を解決したいのか」といった、自社にとって根源的な問いに向き合う機会になります。課題を洗い出す作業を進める中で、これまで意識していなかった潜在的な問題点に気づくのはよくあることです。
さらに、詳細に記述されたRFPは、見落としていた課題をベンダーから指摘してもらうきっかけにもなり得ます。
RFP作成は、現状分析を通じて隠れた課題を明らかにし、将来のビジョンを具体化する、非常に価値のあるプロセスと言えるでしょう。
③候補となるすべてのベンダーを効率よく評価できる
RFPを作成しない場合、発注先候補となる全てのベンダーに対して、要望や要求を言葉で個別に説明しなければなりません。この方法では、各社間で説明内容が違ってしまったり、ベンダー側で異なる解釈が生じたりする可能性があります。結果として各社から多様な提案が寄せられ、評価が極めて困難になってしまいます。
そこで、複数のベンダーに対して同一内容のRFPを提示すれば、各社からの提案内容に大きな差異が生じにくくなります。発注側企業は、提案内容を効率的に比較検討できるので、自社のニーズに合致するベンダーを選定しやすくなるのです。
⚫︎ベンダーの選定基準については、下記資料の第4章を参考にしてください。
「基幹システム再構築の成功法則大全」
④システム開発スケジュールや納期に無理がないか確認できる
社内で計画していたシステム開発のスケジュールや納期が現実的かどうかを、RFPを作成する過程で検証できます。またRFQを作成する際には、想定していた予算が妥当かどうかの評価が可能になります。
プロジェクトの進行に無理があると判明した場合、予算や納期の調整、あるいはスケジュールの再検討といった対策を講じる必要があるでしょう。
⚫︎発注者とベンダで共有しておくべき重要な考え方については、下記資料の第3章を参考にしてください。
「基幹システム再構築の成功法則大全」
⑤トラブル発生を防げる
システム開発の現場で、「必要な要件は伝えたはずだが、完成したシステムが期待したものと異なる」と発注側が主張し、ベンダー側は「発注側から提示された要望に基づいて構築した」と反論するトラブルは少なくありません。
不明確な要求定義や口頭での合意、認識のずれなどが原因となって揉め事になるのです。最終的に訴訟にまで発展してしまうケースもあり、ここまで発展すると解決に長期間を要し、発注側とベンダー側の双方に多大な損害が生じます。
RFPを作成して必要な要件を明らかにすることは、このような不幸なトラブルの発生を未然に防ぐために有効な手段です。
⑥ベンダー側も安心して取り組める
ベンダー側にとって提案書作成には多大な時間と労力がかかるものです。RFPがなく目的や要求内容が不明瞭なまま提案を依頼された場合、ベンダーはその労力に見合わないと感じ提案を辞退する可能性があります。
そのため、RFPを通じて発注側の現状や課題、システムに求める内容などを明確に伝えましょう。その結果、ベンダーは単なる情報収集ではなく、真剣なシステム導入検討であると認識するため、より質の高い提案が期待できます。
RFPの存在は、提案を求められるベンダー側にとって、安心して提案活動に取り組むための重要な要素です。
RFPの記載項目

RFPに定められた書式は存在しませんが、一般的には「概要」「提案依頼内容」「選定の進め方」の3要素を中心に作成されるケースが多いです。ここでは、RFPに最低限含めるべき3つの項目を説明します。
概要
「概要」では、システム開発やリプレイスを検討するに至った経緯、その背景にある事業戦略や経営状況、そして現状のシステムが抱える具体的な問題点を提示します。目指すべきゴールを含め、ベンダーがプロジェクト全体の状況を理解できる情報を記述します。
| 項目 | 内容 |
| 本書の目的 | このRFPの目的・位置付け |
| プロジェクトの背景 | プロジェクトが立ち上がった背景 |
| 現在の課題 | 現在抱えている問題点 |
| システム化の目的 | なぜシステムを導入するのか |
| ゴール | プロジェクトの目標 (品質、費用、納期など) |
| プロジェクトのスコープ | 提案を依頼するプロジェクトの範囲 (システム開発のみか機器の購入や保守も含むか) |
| 会社情報(発注側) | 自社の商品・サービス内容、組織図、システム利用者情報 |
| システム構成 | 現行の社内システム構成図、システムパッケージ |
| 機器情報 | 現行PCやサーバーなどの台数、スペック情報 |
提案依頼内容
ここでは、ベンダーに対して提案書に盛り込んでほしい情報を伝えます。
| 項目 | 内容 |
| 会社情報(開発側) | ベンダーの会社情報、商品・サービス情報、導入事例 (自社と同様の会社規模での業種・業種について) |
| 提案システム概要・構成 | 提案システムの全体像 |
| 機能要件 | システムに実装してほしい機能 |
| 非機能要件 | 性能・拡張性・セキュリティなど、機能面以外で求める要件 |
| 移行要件 (必要な場合のみ) | 現行システムから新システムへの移行に関する要望 |
| 教育要件 (必要な場合のみ) | システムを利用するために必要な教育・研修の要望 |
| 運用保守要件 (必要な場合のみ) | システム導入後の運用・保守に関する要望 |
| スケジュール・体制 | プロジェクトの全体スケジュールや参画メンバー |
| 成果物 | 納品を希望する成果物の一覧 |
| ドキュメントサンプル | 成果物の過去サンプル |
| サポート体制 | システム障害発生時の対応 |
| 概算費用 | 初期費用(イニシャルコスト)や月額費用(ランニングコスト)の見積もり |
| 制約事項 | 現時点で明らかな制約事項やリスク |
| 契約内容 | 契約形態(請負・準委任・派遣など) |
| 支払い方法 | 支払い方法 (一括・分割など) |
選定の進め方
RFPを提出したあと、どのような手順でベンダーの選定を進めていくのかを提示する部分です。
| 項目 | 内容 |
| 選定スケジュール | 提案書の提出期限、プレゼン日程、選考結果の連絡日、 連絡方法など |
| 提案書提出先 | 提出先の名称、住所、担当者氏名、メールアドレスなどの連絡先情報 |
| 評価基準 | 採点方法、評価時に重視するポイント |
一般的に、RFP提出から提案書提出までの期間は、2~3週間程度が目安です。
RFP作成や提出後の流れ

ここでは、RFP作成の全体の流れをまとめました。作成に必要なステップと、RFP提出後のベンダー選定までを以下の順序で進めます。
RFP作成の流れ
RFP作成にはいくつかの段階があります。一般的には、以下のステップで進められます。
- チーム編成: 情報システム部門と業務担当者中心にRFP作成チームを組織し、PMとオーナーを決定。
- 課題洗い出し: 経営層、管理職、現場担当者からヒアリングし、現状の課題と優先順位を明確化。
- 導入目的: システム導入の理由と達成目標を明確に言語化し、プロジェクトメンバーで共有。
- RFI情報収集: 複数ベンダーにRFIを提出し、情報を収集・比較検討し、RFP送付先を絞り込み。
- 要求具体化: ヒアリングとRFIに基づき、課題解決に必要な機能や性能、成果物を具体的に整理し、優先順位付け。
- 評価基準設定: ベンダー提案を比較するための評価項目と判断基準を明確化。
- RFP作成・提出: 上記内容を文書化し、絞り込んだベンダーに提出(必要に応じてRFQも)。
RFP提出後の流れ
RFP(提案依頼書)を提出した後は、以下のようなステップでプロジェクトが進行します。
まずは、各ベンダーから提出された提案書をもとに「提案書評価」を行います。この評価は、事前に設定した評価基準に基づいて実施され、必要に応じて評価シートやプレゼンテーションなども活用しながら、複数のベンダーの提案を比較・検討していきます。評価のポイントには、提案内容の妥当性や実現可能性、コストパフォーマンス、ベンダーの実績・信頼性などが含まれます。
その後、「ベンダー決定・契約」のステップへと進みます。評価結果と見積もりを総合的に判断したうえで、最適なベンダーを選定し、社内の関係部署や意思決定者に報告します。
そのうえで、選定されたベンダーと正式に契約を締結し、プロジェクトが本格的にスタートする流れとなります。
RFPを作成するうえでの9つのポイント

RFP作成における具体的な9つのポイントを説明します。
①目的とゴールを明確にする
このシステムを使って最終的に何を実現したいか、具体的にどのような課題を解決したいかという、本質的な答えはRFPの中で必ず示しましょう。答えを明確に提示すれば、プロジェクトを成功へ導く羅針盤となるからです。
発注側とベンダー側がプロジェクトの目的と達成すべきゴールを共有し、認識を擦り合わせておくことは、その後の開発プロセスにおいて非常に重要です。開発が難航する局面を迎えたとしても、当初共有したRFPを再確認すれば、しなやかな方向修正が可能になります。
②経営層やマネジメント層・現場など多くの人から意見を集める
RFPを作成するにあたっては、部署や役職によってシステムへの要望が異なるため、経営層やマネジメント層、現場部門など、社内のさまざまな立場から広く意見を集めましょう。
一部の部門だけでRFP作成を進めてしまうと、予期せぬ要件の抜け落ちや各部門とのニーズのずれが生じ、導入したシステムが現場で十分に活用されず、プロジェクトが期待通りの成果を上げられないリスクが高まります。要件に漏れがないか、他に考慮すべき点はないかを、関連部署の担当者と密に協議しながらRFPを磨き上げる必要があります。
特に、実際にシステムを利用する現場部門の担当者には、RFP作成の初期段階からの参加を求めると良いでしょう。その結果、現場にプロジェクトへの責任感や主体性が育まれ、のちのシステム開発や導入の段階で、よりスムーズな連携体制が構築できるからです。
③ベンダーとのやり取りで徐々にブラッシュアップしていく
RFPの完成度を高めることに注力しすぎ、RFP作成そのものがゴールになってしまうのは間違いで「RFPは相互理解を深めるためのツール」と捉え、ベンダーとのコミュニケーションを重ねる中で、徐々にその内容を洗練させていく意識を持ちましょう。
RFPはあくまで、手段。ベンダーに対して発注側の意図や要望を正確に伝え、優れた提案を引き出し、その後のシステム開発を円滑に進めることが最終的な目的です。したがって、最初から完璧な出来でなくても構いません。
④システムに対し期待していることを抜け漏れなく記載する
RFPには、システムに対して期待する機能はもちろんのこと、考えられるすべての要望を明記しましょう。記載がないことが原因で後々追加費用が発生したり、スケジュールが遅延したりするなどの問題を避けるためです。
システムに実装してほしい機能に加えて、障害時のサポート体制、データのバックアップ、セキュリティ対策といった機能面以外の事柄についても、漏れなく記述する必要があります。
ただし、要望するすべての要件を同じ重要度で記載すると、RFPの焦点がぼやけ、曖昧な内容になってしまいます。そのため「必須要件」と「推奨要件」のように、優先順位を明確にしながら記述していくことがポイントです。
⑤自社に見合わないオーバースペックな要件を記載しない
RFPには、システムに期待する要素をもれなく記述することは重要ですが、同時に、過剰な要件を盛り込むのは避けるべきです。自社の規模や予算に見合わない過度な要求を記載すると、ベンダーから予算を大幅に上回る見積もり金額が提示される可能性があります。
そうなると、プロジェクトが初期段階で立ち往生してしまいかねません。RFPに要件を記載する際には、その内容が本当に必要不可欠なものなのか、実現可能な範囲であるのかを慎重に検討し、現状を踏まえた内容に留めるよう心がけましょう。
⑥RFP提出後の追加要求はなるべくしない
RFPを提出する前に、必要と思われる要件が全て網羅されているかを社内で慎重に確認しましょう。RFP提出後の追加要件の提示は、原則として避けるべきです。
ベンダーは、提出されたRFPに基づいて提案書や見積書を作成するため、後から要件が追加されると、スケジュールの再調整や提案書・見積書の修正といった追加作業が発生し、プロジェクトの遅延を招く要因となります。発注側にとっても、稟議手続きやスケジュールを検討し直すという、無駄な労力を要してしまいます。
⑦スケジュールや予算を明確に記載する
RFPには、貴社が想定するベンダー選定の期間、システム構築にかける期間、そしてシステムの本稼働を目指す時期といったスケジュールを大まかに示しておくと親切です。日どりがあまりにも不明確な場合、ベンダーは適切な人員配置計画や見積もりの立案が難しくなります。
RFPに予算を含めるべきかどうかは意見が分かれますが、資金的な制約の中でプロジェクトを推進するためには、可能な範囲で予算の記載をおすすめします。優先度が低い課題解決も含める提案と、優先度の高い課題解決のみにしぼった提案など、2〜3種類に分けて予算の提示を依頼してみるのも一つの手段です。
⑧RFPの作成と同時に客観的な評価基準を作成しておく
RFPの作成と並行して、ベンダーから提出される提案書を評価するための客観的な基準を策定しておくのも、非常に重要なポイントです。方法としては「ベンダーの技術力や過去の実績は十分か」「提示されたスケジュールや見積もり金額は妥当か」といった評価項目をまとめたシートやチェックリストを作成します。
事前に明確な評価基準を作成してRFPに明記しておけば、ベンダーは貴社のニーズを的確に捉えた、より質の高い提案をしやすくなります。さらに、最終的な発注先ベンダー決定後に、社内からの異論を抑制する効果も期待できます。ベンダー候補を横並びで比較評価していけば、貴社にとって最適なパートナーを円滑に選定できるでしょう。
⑨専門家に相談する
RFPの作成、必要な情報の網羅的な記載、そして自社に最適なベンダーの選定は、多くの企業担当者様にとって頭を悩ませる課題です。その場合、専門家に相談するのがおすすめです。
企業のデジタル変革を支援するオーシャン・アンド・パートナーズ株式会社は、多様な専門性を持つプロフェッショナルが集結したチームで、お客様の基幹システム再構築を強力にサポートいたします。
15年の経験を持つ私たちのチームは、最新テクノロジーの潜在能力を深く理解し、戦略策定からビジネスへの実装、そして変革の実現まで、事業戦略全体をデザインいたします。
⚫︎詳細はこちらからご覧ください
「基幹システム再構築の成功法則大全」
RFPについてのご相談は オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社まで

この記事では、RFPと要件定義書の根本的な違いや、RFIやRFQとの関連性を解説。さらに、質の高い提案を引き出すRFP作成における9つの重要ポイントをまとめました。RFPの作成には相応の労力がかかりますが、初期段階での丁寧な準備が後のリスクを軽減し、プロジェクト全体の価値を高めて成功に繋がることは間違いないでしょう。
基幹システムを再構築するプロジェクトの成功率は、わずか3割に過ぎないと言われています。発注者とベンダーとの関係に成否を占う重要なポイントを、下記の資料で詳しく解説しました。プロジェクト検討やスタートの際にぜひご活用ください。
⚫︎ホワイトペーパー「基幹システム再構築の成功法則大全」
RFP作成が初めての方やご経験の浅い方はもちろん、システム開発の外注先選びにお困りの方も、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の課題解決に向け、専門知識を結集したチームが親身になってご支援させていただきます。
この記事を書いた人について
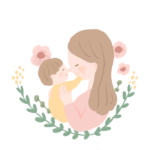
-
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会社
一児の母として子育てに奮闘しながら、オーシャン・アンド・パートナーズの代表者および技術チームメンバーの補佐に従事。
実務の現場に寄り添い、日々の会話や支援を通して見えてきた“リアル”を、等身大の視点でお届けしています。